| <<慜偺儁乕僕 | 師偺儁乕僕>> |
| 2004擭1寧28擔乮悈乯 |
| 搚擔偼乽戞俁夞丂擔杮庤榖捠栿巑嫤夛丂堦攽尋廋夛乿偵嶲壛偟偰偒傑偡丅 |
|
丂嬥偑側偄偭偪傘偆偺偵丄侾寧俁侾擔乮搚乯乣俀寧侾擔乮擔乯偵嶳棞導峛晎巗偱峴傢傟傞擔杮庤榖捠栿巑嫤夛偺暯惉侾俆擭搙戞俁夞堦攽尋廋夛偵嶲壛偟偰偒傑偡丅
丂巑嫤夛偺尋廋夛側傫偰堌傟懡偔偰偙傟傑偱宧墦偟偰偒偨偺偱偡偑丄弶怱偵曉偭偰曌嫮偟傛偆両偲偄偆崱擭偺儌僢僩乕偵廬偭偰丄弶嶲壛偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅
丂偄偭偨偄偳偆側傞偙偲傗傜丄偲偰傕怱攝偱偡偑丄傑偁丄巑摨巑偲偄偆偙偲偱丄崱巒傔偰偄傞堦師帋尡懳嶔偵偮偄偰偺忣曬側偳傕暦偗偨傜偄偄側偲巚偭偰偄傑偡丅
丂僥乕儅偼乽惌尒曻憲庤榖捠栿乿偱偡丅擔忢揑偵偼偁傑傝墢偑偁傝傑偣傫偑丄崱擭偺壞偵偼嶲媍堾慖嫇偑偁傞偙偲偱偡偟丄壗偐彮偟偱傕堬忛偵帩偪婣傟傞傛偆偄傠偄傠忣曬廂廤偟偰偒偨偄偲峫偊偰偄傑偡丅
|
|
|
|
| 2004擭1寧26擔乮寧乯 |
| 庤榖捠栿幰尋廋丒敀郪偝傫偺島媊 |
|
丂偐側傝抶傟偰偟傑偭偨偺偱偡偑丄儚乕僋僸儖搚塝偱峴傢傟偨庤榖捠栿幰尋廋偵嶲壛偟偰偒傑偟偨丅
丂島巘偼敀郪杻媩偝傫偱丄嵟弶偐傜僶僢僠僔暦偒偨偐偭偨偺偱偡偑丄侾帪娫敿傕抶崗偟偰偟傑偭偨丅
丂嫵幒偵擖傞偲崟斅丄偱偼側偔僾儘僕僃僋僞乕偵乽晅壛偺椺乿偲偺斅彂丄偲偼尵傢側偄側乧丄偲塮偟弌偝傟偰偄傑偟偨丅
丂斵彈偺愢柧偵傛傟偽亙擔杮岅偱尵傢傟偨帪丄傁偭偲庤榖傪巚偄偮偐側偄傛偆側暥復亜傪捠栿偡傞応崌偵偼丄偳偆偟偰傕偦偺暥復偑帩偭偰偄偨亙枴傢偄亜偩偲偐亙暤埻婥亜側偳偑敳偗棊偪偨昞尰偵側偭偰偟傑偄偑偪偩丅偦傫側応崌偵巹偨偪偼丄偮偄亙帺暘偱張棟偱偒傞斖埻偺昞尰偵娙棯壔偟偰捠栿偟偰傛偟偲偟偰偟傑偆亜偙偲偑懡偄丅偦偙傪壗偲偐忔傝墇偊傜傟側偄偐丄偲偄偆偺偑敀郪偝傫偺栤偄偐偗偩偭偨傛偆偵巚偆丅
丂傑偨丄傠偆幰偺巜揈偲偟偰亙堦偮堦偮偺庤榖偼暘偐傞傫偩偗傟偳傕丄慡懱偲偟偰偺堄枴偑偮偐傔側偄亜捠栿偲偐丄亙暥偲暥偲偺偮側偑傝偑暘偐傜側偄亜捠栿偑偄傞偲偄偆丅
丂偦偟偰丄偦傟傜傪忔傝墇偊傞僉乕偵側傞偙偲偺堦偮偑丄乽儘乕儖僔僼僩乿偱偼側偄偩傠偆偐偲偺偙偲丅
丂戝曄柺敀偄巜揈偩偭偨丅徻嵶偼傑偨暿偺婡夛偵彂偄偰傒偨偄丅
|
|
|
|
| 2004擭1寧23擔乮嬥乯 |
| 撉傒庢傝帋尡偼僐儈儏僯働乕僔儑儞擻椡傪應傟側偄両丠 |
|
侾寧俀侾擔乮悈乯偺挬擔怴暦挬姧偺乽巹偺帇揰乿偵搶嫗妛寍戝妛嫵堢妛晹晅懏崅峑戝愹峑幧嫵桜乮塸岅乯偺嶚揷丂娹乮偝偝偩丂偄傢偍乯偝傫偑丄師偺傛偆偵彂偄偰偄偨丅
乭戝妛擖帋僙儞僞乕偺俀侽侽俇擭搙帋尡偐傜丄塸岅偵儕僗僯儞僌乮暦偒庢傝乯僥僗僩偑摫擖偝傟傞丅
崅峑偱偺壒惡僐儈儏僯働乕僔儑儞廳帇偺庼嬈傪懀偡偺偑慱偄偲偄偆丅偩偑丄恖娫揑姶惈傗巚峫椡偺堦憌偺掅壓傪彽偔側偳丄傓偟傠暰奞偑懡偄偺偱偼側偄偐丅
丂栤戣偺戞堦偼丄恖娫偺慡恖奿偵娭傢傞乽僐儈儏僯働乕僔儑儞擻椡乿傪丄婡婍傪巊偭偨扨弮側暦偒庢傝僥僗僩偲寢傃偮偗傞敪憐偺昻崲偝偵偁傞丅
丂塸岅傪捠偟偰丄擔杮恖偲奜崙恖偑忣曬傗堄尒傪岎姺偡傞応崌丄椉幰偼偍屳偄偺姶忣傗攚宨偵側傞抦幆丄尵岅擻椡側偳傪柍堄幆偵撉傒庢傝側偑傜丄榖戣傗岅渂丄榖偡僗僺乕僪傪丄憡屳棟夝偑壜擻側傛偆偵愨偊偢挷惍偟崌偄丄僕僃僗僠儍乕側偳傕岎偊偰丄夛榖偺懀恑偵搘傔偰偄傞丅
丂偙偆偟偨姶惈丄抦惈傪憤摦堳偟偨憃曽岦偺嫟摨嶌嬈偑丄僐儈儏僯働乕僔儑儞偱偁傞偼偢偩丅壒惡婡婍傪捠偟偨忣曬偺堦曽揑側揱払偼丄儔僕僆曻憲偐岞嫟偺応偱偺傾僫僂儞僗偖傜偄偩傠偆丅暦偒庢傞擻椡偑偁傞偵墇偟偨偙偲偼側偄偑丄戝妛擖帋偵嵦傝擖傟傞傎偳丄桪愭弴埵偑崅偄暔偩傠偆偐丅乮埲壓棯乯乭
丂巹偵傕偙偺斸敾偑摉偨傞晹暘偑偁傞側丄偲姶偠偨丅偲偄偆偺傕丄庤榖捠栿巑偺擇師帋尡懳嶔島嵗傪捠偠偰丄乽撉傒庢傝帋尡傪撍攋偡傞偵偼丄傕偭偲價僨僆傪偠偭偔傝尒偰僩儗乕僯儞僌偡傞昁梫偑偁傞丅乿偲峫偊偰偄偨偐傜偩丅
丂抧堟偱傠偆幰偲岦偒崌偄側偑傜挿偄娫嫟偵曕傫偱偒偨庤榖捠栿幰偑丄埬奜價僨僆偺撉傒庢傝偑嬯庤側偙偲偑偁傞丅巑偺擇師帋尡傪偳偆偟偰傕撍攋偱偒側偐偭偨傝偡傞丅
丂巹偼丄偦偆偟偨拠娫偵愙偟偰丄乽傕偭偲帋尡懳嶔偲妱傝愗偭偰巜摫偡傞昁梫偑偁傞偺偱偼側偄偐乿偲忢乆姶偠偰偒偨丅帋尡偱栤傢傟偰偄傞偺偼丄僐儈儏僯働乕僔儑儞擻椡偱偼側偔丄扨側傞抦幆偲媄弍側偺偩丄偲丅
丂偟偐偟丄偙偺婰帠傪撉傫偱偪傚偭偲乽堦柺揑夁偓偨偐側乿偲姶偠偨丅
丂乽堦曽揑偵庤榖忣曬傪壒惡擔杮岅偵抲偒姺偊傞乿嶌嬈偑媮傔傜傟傞庤榖捠栿幰偺媄弍悈弨傪寁傞庤榖捠栿巑媄擻擣掕帋尡偵偲偭偰丄價僨僆偵傛傞撉傒庢傝椡偑帋偝傟傞偙偲偼丄偁傞柺昁梫側帋尡偲傕尵偊傞丅廬偭偰丄戝妛擖帋傊偺暦偒庢傝帋尡摫擖偺揔斲偲偼丄師尦偺堘偆榖偐傕偟傟側偄丅
丂偗傟偳傕丄彮側偔偲傕乽庤榖捠栿巑梴惉乿偲偄偆棫応偐傜偼丄傗偭傁傝憃曽岦僐儈儏僯働乕僔儑儞偺嫶搉偟傪偡傞椡偙偦堢偰側偗傟偽側傜側偄偺偐側丄偲姶偠偨丅
|
|
|
|
| 2004擭1寧20擔乮壩乯 |
| 庤榖捠栿巑堦師帋尡懳嶔乽崙岅乿嶲峫彂 |
|
乽擔杮岅梫愢乿傪捠嬑搑忋偱撉傒巒傔偨偺偱偡偑丄擄偟偔偰偝偭傁傝撪梕偑摢偵擖偭偰偒傑偣傫丅慜搑懡擄偱偡丅愱栧梡岅偺奣擮偑棟夝偱偒偰偄側偄偙偲偑尨場側傫偩傠偆偲偼巚偆偺偱偡偑丄撉傫偱偄偰傕帤柺傪捛偆偽偐傝偱撪梕偑棟夝偱偒偢丄廬偭偰摢偵壗傕巆傝傑偣傫丅暥復傪撉傒廔傢傞偲壗傪尵偄偨偄暥復偩偭偨偺偐偑丄傑傞偱尵偊側偄偺偱偡丅
偙傟偭偰丄晛抜巹偺庤榖捠栿傪尒偰偄偰偔傟傞傠偆幰偺婥帩偪偵嬤偄偐傕乧側偳偲柇偵娭怱偟偨傝偟偰偄傑偡丅
乽孹岦偲懳嶔乿偵嶲峫彂偲偟偰庢傝忋偘偰偁偭偨妛寍恾彂乮姅乯偺怴曇乽崙岅梫愢乿偱偡丅斾妑揑敄偄嶜巕偱壙奿傕侾侽侽侽墌側偺偱丄偙傟偼曌嫮嵽椏偵嵟揔偐傕偲桬傫偱攦偭偰傒偨偺偱偡偑丄敪峴擭偑屆偄暘傕偭偲擄偟偐偭偨丅斶偟偄丅
偦傟偱傕堦惗寽柦撉傕偆偲偡傞偺偱偡偑丄抧壓揝傗僶僗偵忔傞偲偡偖偵柊偔側偭偰偟傑偭偰曌嫮偵側傝傑偣傫丅壗偲偐婥崌偄擖傟捈偝側偒傖両
|
|
|
|
| 2004擭1寧19擔乮寧乯 |
| 戝妛擖帋僙儞僞乕帋尡 |
|
嶐擔堦嶐擔偲戝妛擖帋僙儞僞乕帋尡偑偁偭偨偦偆偱丄崱挬偺怴暦偵栤戣偲夝摎偑嵹偭偰偄傑偟偨丅
庤榖捠栿巑堦師帋尡偺曌嫮夛傪巒傔偨娭學偱乽崙岅偺栤戣偼偳傫側撪梕側傫偩傠偆側丠乿偲娭怱傪帩偪傑偟偨丅
崙岅嘥丒崙岅嘦偺栤戣偼戝偒側愝栤偑係偮丅戞俁栤偼屆暥乮栤侾乣栤俇乯丄戞係栤偼娍暥乮栤侾乣栤俇乯偱偟偨丅廬偭偰庤榖捠栿巑堦師帋尡偺嶲峫偵側傝偦偆側偺偼戞侾栤乽挳廜偺亀億僗僩儌僟儞亁丠乿乮搉曈桾乯偲戞俀栤乽岇帩堾尨偺揋摙偪乿乮怷墾奜乯偺挿暥撉夝栤戣偱偟偨丅
傑偩丄傗偭偰傒偰傑偣傫偑丄崱擭偙偦偼挧愴偟偰傒傛偆偲峫偊偰偄傑偡丅
俀寧偺曌嫮夛偱偼丄巑帋尡偺乽崙岅乿傪傗傞梊掕側偺偱丄嶲峫彂傪扵偟巒傔傑偟偨丅
偲傝偁偊偢杮壆偺揦摢偱乽擔杮岅梫愢乿乮岺摗峗傎偐丒傂偮偠彂朳侾俋侽侽墌亄惻乯傪尒偮偗偰攦偭偰偒傑偟偨偑丄弶偭傁側偐傜撪梕偑擄偟偔偰傔偘偰偄傑偡丅
傑偨丄乽孹岦偲懳嶔乿偵徯夘偝傟偰偄偨乽擔杮岅奣愢乿亙娾攇僥僉僗僩僽僢僋僗亜乮娾攇彂揦俀係侽侽墌乯傕傾儅僝儞丒僪僢僩丒僐儉偱拲暥偟傑偟偨丅
崙岅偺曌嫮側傫偰媣偟傇傝偱偡偑丄婃挘偭偰傒傑偡丅
|
|
|
| 2004擭1寧10擔乮搚乯 |
| 柧擔丄愮梩導偺傠偆廳暋忈奞幰塣摦偵娭偡傞島墘夛偑偁傝傑偡丅 |
|
柧擔丄侾寧侾侾擔乮擔乯屵屻侾帪傛傝彫栰愳岞柉娰偱乽愮梩導偺傠偆廳暋忈奞幰庼嶻巤愝寶愝塣摦乿傪僥乕儅偵擔梛嫵幒偑奐偐傟傑偡丅
島巘偼愮梩導傠偆廳暋幰巤愝傪嶌傞夛暃夛挿丂屲廫棐丂徍抝偝傫偱偡丅暃夛挿偝傫偱偡偐傜丄愮梩導傠偆嫤偺栶堳偝傫偱偟傚偆偐丠杔偼偦偺庤榖捠栿傪埶棅偝傟傑偟偨丅偱偒傟偽暦偒庤偲偟偰嶲壛偟偨偐偭偨偺偱偡丄擔梛偱側偄偲側偐側偐埶棅傪庴偗傟傜側偄偟丄偙偺島墘夛偼偦傕偦傕嶲壛偟傛偆偲梊掕偟偰偄偨偺偱丄庤榖捠栿傪抐偭偰嶲壛偡傞偺傕儅僘僀傛側丅
愮梩偺巤愝寶愝塣摦偵偼儂乕儉儁乕僕偑偁傝傑偟偨丅
|
|
|
| 2004擭1寧4擔乮擔乯 |
| 庤榖捠栿巑堦師帋尡曌嫮傪柧擔偐傜僗僞乕僩 |
|
丂暯擭傛傝俀擔挿偄搤媥傒傕偲偆偲偆廔傢偭偰偟傑偄傑偟偨丅柧擔偐傜巇帠偱偡丅偲傝偁偊偢偼係寧偺暔壙僗儔僀僪夵掕偵岦偗偰偺弨旛偑巒傑傞偺偱丄婥崌偄擖傟偰摥偐偹偽偲巚偭偰偄傑偡丅傕偆彮偟婎慴曌嫮傪偟偨偐偭偨偺偱偡偑丄偁偲偼憱傝側偑傜曌嫮偡傞姶偠偱偡丅
丂偦偟偰丄傕偆堦偮庤榖捠栿巑堦師帋尡偵岦偗偰偺曌嫮傕乮儂儞僩偼搤媥傒拞偵僗僞乕僩愗傝偨偐偭偨偺偱偡偑乧乯柧擔偐傜僗僞乕僩偟傛偆偲峫偊偰偄傑偡丅丂傑偢偼丄夁嫀栤戣廤乽庤榖捠栿媄擻擣掕帋尡丂孹岦偲懳嶔亅庤榖捠栿巑帋尡崌奿傊偺摴乿傪撉傒巒傔傛偆偲巚偭偰偄傑偡丅
丂偙偺夁嫀栤廤偼俀侽侽侽擭乮暯惉侾俀擭乯俇寧偵弌斉偝傟偨乽庤榖捠栿巑帋尡丂孹岦偲懳嶔乿偑慡柺夵掶偝傟偨傕偺偱偡偑丄慜偺傕傎偲傫偳撉傑偢偵愊傫偱偁偭偨偺偱丄崱搙偙偦偟偭偐傝撉傒偙側偦偆偲巚偭偰偄傑偡丅巑堦師帋尡懳嶔偲巚偭偰偁傟偙傟峫偊偰傒偨偺偱偡偑丄傗偭傁傝側偐側偐曌嫮寁夋傪棫偰傞偙偲帺懱偑擄偟偄偱偡偹丅
丂偲傝偁偊偢夁嫀栤撉傫偱偦傟偐傜峫偊傛偆偲偄偆嶌愴偱偡偑丄帋尡壢栚偑俆壢栚傕偁傞乮侾丏忈奞幰暉巸偺婎慴抦幆丄俀丏挳妎忈奞幰偵娭偡傞婎慴抦幆丄俁丏庤榖捠栿偺偁傝曽丄係丏崙岅丄俆丏庤榖偺婎慴抦幆乯偺偱丄侾寧拞偵偼栚張傪棫偰側偄偲侾寧偱侾壢栚曅偯偗傞偲偟偰傕俀寧乣俇寧偐偐偭偰偟傑偆傢偗偱偡偐傜丄寛偟偰梋桾偼側偄偲巚偭偰偄傑偡丅
丂偦偟偰俈寧偵偄偭偨傫憤傑偲傔傪傗偭偰丄抦幆偺惍棟偲埫婰傪傗偭偰丄俉寧偵偼夁嫀栤傪擭戙傪慿偭偰侾侽擭暘偔傜偄傗傝丄俋寧偼嵟廔揑側埫婰偵廤拞偡傞丅偲偄偆傛偆側僗働僕儏乕儖傪敊慠偲峫偊偰偄傑偡丅偝偰丄偳偆側傞偙偲傗傜乧丅偪側傒偵嶐擭偺堦師帋尡偼俋寧俀俉擔偱偟偨偐傜丄摨偠俋寧戞係廡偲峫偊傟偽俋寧俀俇擔乮擔乯傪栚巜偡偙偲偵側傝傑偡丅慡崙偺巑傪栚巜偟偰偄傞奆偝傫丄婃挘傝傑偟傚偆丅
|
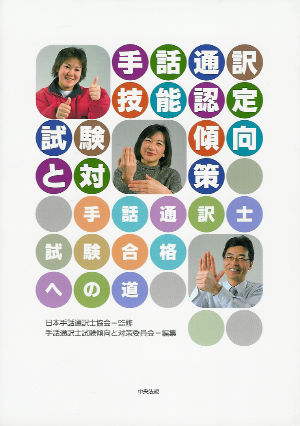 |
|
|
| 2004擭1寧2擔乮嬥乯 |
| 弶攧傝弶峴楍 |
|
崱擔丄偨傑偨傑尨廻偵峴偔梡帠偑偁偭偰丄幵偱昞嶲摴偐傜柧帯捠傝偺抾壓捠傝曽柺偵嬋偑偭偨偺偱偡偑丄傕偺偡偛偄峴楍両
僷儗僼儔儞僗偲偄偆價儖偺慜偐傜柧帯捠傝傪怴廻曽岦偵暲傫偱傞暲傫偱傞丅搶嫿恄幮傪夁偓偰傕傑偩暲傫偱傞丅恄媨慜侾挌栚偺岎嵎揰傪夁偓偰丄嶁傪搊傝偐偗偰傕暲傫偱傞丅
寢嬊係乣俆侽侽儊乕僩儖偼偁偭偨偲巚偄傑偡丅侾儊乕僩儖偵俇恖偲偟偰傕俁侽侽侽恖偔傜偄偄偨偺偐側丅偦傟傕惓寧俀擔偺挬俋帪偩傛丅側傫偱傕挬俈帪偐傜攧傝弌偟偰傞桳柤側偍揦偑偁傞傜偟偄丅
偦偺偁偲廰扟偵傕婑偭偨偺偱偡偑丄偙偪傜偱傕侾侽俋乮僀僠儅儖僉儏乕乯偺價儖偱偼抧壓偵偛偭偦傝暲傫偱偄偨偦偆偱偡丅嫲傞傋偟庒幰偨偪丅
偲巚偭偰偄偨傜丄搶媫杮揦偵偼偡偱偵揦撪偱懸偭偰傞偍偽偼傫偨偪偑偄偨丅偦偺屻怴廻墂惣岥偵夞偭偨偺偱偡偑丄偙偪傜偼嫗墹僨僷乕僩丄彫揷媫僨僷乕僩慜偵偠偠丒偽偽偑偛偭偦傝丅
偙傟偑宨婥傕忋岦偄偰偒偰偄傞徹嫆偩偲偄偄偱偡偹丅
|
 |
|
|
| 2004擭1寧1擔乮栘乯 |
| 偁偗傑偟偰偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅 |
|
怴擭偺偁偄偝偮偼侾俀寧俁侾擔偺栭拞偵彂偔偺偑偄偄偺偱偟傚偆偑丄杔偺応崌偼丄枅擭擭枛偺弨旛偑抶傟偰丄惓寧偵擖偭偰偐傜戝憒彍傗偭偨傝偟偰傞偺偱丄偳偆偟偰傕乽偍惓寧婥暘乿偼偪傚偭偲抶傟偰傗偭偰偒傑偡丅
崱擔傕丄傗傝巆偟偨偍晽楥憒彍傪偣偭偣偣偭偣偲傗偭偰偍傝傑偟偨丅偦傟偱侾寧侾擔偺怺栭偵崱偙偆偟偰彂偄偰偄傞傢偗偱偡丅
偙偺擭枛擭巒偼丄俁偮偺偙偲傪傗傝偨偄側偲巚偭偰偄傑偟偨丅堦偮栚偼僠儍僀儖僪杮幮偺曐堢嶨帍娭學偺帒椏惍棟丅俀偮栚偼傾僋僙僗乮僨乕僞儀乕僗僜僼僩乯偺捠怣島嵗丅偦偟偰俁偮栚偑庤榖捠栿巑堦師帋尡曌嫮夛偺弨旛偱偡丅
擭枛擭巒偺偍媥傒偭偰戝掞寁夋搢傟偵側傞偺偱偡偑丄偲傝偁偊偢崱擔偼僠儍僀儖僪偺帒椏傪惍棟偟偰乽偣偨偮傓傝乿忋偵傾僢僾偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅
巊偭偰偄傞儂乕儉儁乕僕僜僼僩乽俬俛俵儂乕儉儁乕僕價儖僟乕俉乿偺怴婡擻偵丄偙偺擔婰嶌惉偲嫟偵僷僗儚乕僪偺愝掕偲偄偆偺偑偁偭偨偺偱丄憗懍偦傟傪巊偭偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅帒椏摍傪儂乕儉儁乕僕忋偵曐懚偟偰偍偔偙偲偼曋棙側偺偱偡偑丄傑偩嶌惉拞偱岞奐偱偒側偄帒椏側偳傪僷僗儚乕僪傪偐偗偰曐岇偟偰偍偔傢偗偱偡丅
僼傽僀儖傪僱僢僩忋偵曐懚偡傞曽朄偲偟偰偼丄僕儍僗僩僔僗僥儉偺傾僀僨傿僗僋傗儎僼乕偺僽儕乕僼働乕僗側偳傕棙梡偟偰偄傑偡偑丄庤榖娭學偺帒椏偼帺暘偺儂乕儉儁乕僕偵捈愙擖傟偰偍偗傞偲堦斣巊偄傗偡偄偱偡丅
儎僼乕偼丄嫀擭巑梴惉島嵗偺弨旛偱儎僼乕僌儖乕僾偲偄偆僌儖乕僾僂僃傾傕巊偭偰傒傑偟偨丅杔偲偟偰偼偲偰傕曋棙偩偲巚偭偨偺偱偡偑丄儊儞僶乕偵傛偭偰僀儞僞乕僱僢僩偺棙梡娐嫬偵嵎偑偁傝丄傑偨巊偄曽偺廗摼偵傕偽傜偮偒偑弌偰丄寢嬊弨旛抜奒偩偗偺棙梡偲側偭偰偟傑偄傑偟偨丅
崱屻丄偙偆偟偨僱僢僩忋偺忣曬岎姺偑傛傝娙扨偵偱偒傞傛偆偵側偭偰偄偗偽丄杔傜偺傛偆側巗柉塣摦偺忣曬嫟桳傕奿抜偵恑傓偲巚偄傑偡丅
|
 |
|
|
| 2003擭12寧30擔乮壩乯 |
| 懹懩側堦擔 |
|
崱擭偺搤媥傒偼偪傚偭偲偩偗挿偄偺偱偁傟傗傠偆偙傟傕偟傛偆偲峫偊偰偄傞偺偱偡偑丄幚嵺偵偼晹壆偺曅偯偗偱廔傢偭偰偟傑偭偨傝丄僥儗價偺廃傝傪曅偯偗偮偄偱偵偦偺屻偢偭偲僥儗價傪尒偰偟傑偭偨傝丄忣偗側偄夁偛偟曽偵側偭偰偄傑偡丅
傂偺庤榖僒乕僋儖帪戙偺帒椏傕昁梫側傕偺偩偗敳偒弌偟偰張暘偟傛偆偲峫偊偰偄偨偺偱偡偑丄幚嵺偵僲乕僩傪撉傒弌偡偲偲偰傕娙扨偵偼幪偰傜傟側偔偰丄寢嬊傑偨敔偵栠偟偰曐娗偟偰偍偔傛偆側揥奐偵側傝偦偆偱偡丅
妛惗帪戙偼帪娫傕偁偭偨偟丄庤榖傕巒傔偰嵟弶偺俀乣俁擭偑堦斣怢傃傞偭偰偄偆偗偳丄僲乕僩偺彂偒崬傒傪撉傒曉偡偲帺暘偑柌拞偵側偭偰偨偺偑傂偟傂偟偲揱傢偭偰偒傑偡丅偱傕丄崱偩偭偨傜傕偭偲堘偆儊儌偵側偭偰偄偨傫偩傠偆側偀乣偲偄偆巚偄傕偟傑偡丅
偮傑傝摉帪偺庤榖偺偲傜偊曽偼偁偔傑偱傕乽庤榖偼扨岅儗儀儖偱妎偊偰丄壒惡岅偺弴昞偣偽偄偄偭偰嫵偊傜傟偰傑偟偨丅庤榖偵偼乭偵偰偵傪偼乭偼偁傝傑偣傫丄偲傕嫵傢偭偰偄傑偟偨丅枹偩偵偦傫側乽庤榖娤乿偐傜姰慡偵偼帺桼偵側傟偰偄側偄帺暘偵傕偳偐偟偝傪姶偠偰偄傑偡丅
乽堦斣嵟弶偵偪傖傫偲偟偨擔杮庤榖偺巜摫幰偵弌夛偊偰偄傟偽乧乿偲巚偆偗傟偳丄扤傪崷傓偲偄偆偺偱傕側偔丄偨偩崱偺帺暘偺椡晄懌偐傜偦傫側棟桼偱摝偘傛偆偲偟偰偄傞偩偗偐傕偟傟傑偣傫丅
棃擭偼庤榖偺曌嫮堦偐傜傗傝捈偡偧乣偭偰巚偭偰偄傑偡丅
|
 |
|
|
| 2003擭12寧28擔乮擔乯 |
| 棃擭偺楋乮偙傛傒乯 |
|
杔偼枅擔儎僼乕偺愯偄傪尒偰堦婌堦桱偟偰偄傑偡偑丄怴暦壆偝傫偑擭枛偵側傞偲偔傟傞乽崅搰楋乿傕偗偭偙偆儅僕偱撉傫偱偄傑偡丅
暯惉侾俆擭偼乽搶嫗恄惓娰憼斉丂崅搰楋乮崅搰楋弌斉杮晹曇嶽乯乿傪垽撉偟偰偍傝傑偟偨丅
枅寧乽巐椢栘惎乿偺棑傪尒偰丄乽崱寧偼怲廳偵偙偲傪恑傔傛偆乿偲偐丄乽抁婥傪婲偙偝側偄傛偆偵拲堄偟傛偆乿偲偐巚偆傢偗偱偡丅偦傟偱傕偮偄偮偄徴摦攦偄偟偰庤帩偪偺偍嬥偑彫慘偩偗偵側偭偰偟傑偭偨傝丄傗傜側偒傖偄偗側偄偙偲傪偳偆偟偰傕偱偒側偔偰僟儔僟儔夁偛偟偰偟傑偭偨傝偲偄偆偙偲偽偐傝側偺偱丄偁傑傝楋偺嫵孭傪栶棫偰偰偄傞偲偼尵偄擄偄偺偼帠幚偱偡丅
悽偺拞晄嫷偱偲偆偲偆怴暦壆偝傫傕楋傪偔傟側偔側偭偰偟傑偭偨偺偱丄巇曽側偔攦偄偵峴偭偨偲偙傠丄側傫偲堦斣埨偄俁侽侽墌偺偼偡偱偵攧傝愗傟偰偄傑偟偨両嬃偄偨丅偦偟偰崱擔揹榖偱暦偄偨傜丄偦偺師偺侾侽侽侽墌偺傕偡偱偵攧傝愗傟偱丄巆偭偰偄傞偺偼侾俁侽侽墌偲侾俆侽侽墌丄俀侽侽侽墌偺偟偐側偄偲偺偙偲丅彂揦偺僆儎僕偵尵傢偣傟偽乽俀侽侽侽墌偺偑堦斣摉偨傞乿偦偆偱偡丅乮偦傝傖丄偦偆偄偆傛側丅乯
乽攧傝愗傟偐偀乣崲偭偨側偀乿偲彂揦撪傪偆傠偆傠偟偰偄偨偲偙傠丄偦偺僆儎僕偑姪傔偰偔傟偨偺偑乽侾俀巟偱奐偔偁側偨偺塣惃両丂廫擇巟塣惃曮娪乿乮搶梞塣惃妛夛曇嶽丂係俀侽墌丂摽娫彂揦乯偱偡丅彂揦偺僆儎僕偑尵偆偵偼乽姳巟暿偵暘偐傟偰偰丄偙傟偑堦斣摉偨傞丅壌傕彜岺夛偺夛媍偲偐偁傞帪偼丄昁偢偙傟撉傫偱偄偔偲壗偐寛傔傞偲偒偵傕偄偄丅乿偲偺偙偲丅
乽傾儂偔偝乿偲巚偄側偑傜傕寢嬊攦偭偰偟傑偆巹偱偟偨丅
侾俀俉儁乕僕偩偰偵傕娭傢傜偢係俀侽墌偲戝曄僐僗僩僷僼僅乕儅儞僗偵桪傟偰偄偰丄偟偐傕侾丏婎慴抦幆丄俀丏僇儗儞僟乕丄俁丏崱擭偺塣惃乮憤崌丄寬峃塣丄嬥塣丄巇帠塣丄恖娫娭學丄壠懓塣丄楒垽丒堎惈塣丄寢崶丒垽忣塣乯丄係丏枅寧丒枅擔偺塣惃丄偝傜偵偼俆丏惗傑傟寧暿偺塣惃丄嬨惎暿塣惃丄俇丏憡惈塣傑偱偡傋偰懙偭偰偄傑偡丅乮壗偑乽慡偰乿側偺偐栿暘偐傜側偄傛偹乧丅乯
偩偐傜偳偆偟偨丠偲尵傢側偄偱丄偁側偨傕閤偝傟偨偲巚偭偰偍攦偄媮傔偵側偭偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丠乮閤偟偰傞偐偳偆偐偼暘偐傜側偄偗偳丄杮壆偺弍拞偵丄偁偭偝傝偼傑偭偰婌傫偱攦偭偰傞壌偼傗偭傁傾儂偐傕乧乯
|
 |
|
|
| 2003擭12寧26擔乮嬥乯 |
| 擭夑忬彂偒偟側偑傜丄巚偭偨棃擭偺儌僢僩乕 |
|
擭夑忬傪嶌傝側偑傜崱擭堦擭傪怳傝曉偭偨傝丄棃擭偺偙偲傪峫偊偨傝偟傑偟偨丅棃擭偺儌僢僩乕偼乽慡椡傪偮偔偣乿偵偟傑偟偨丅
僥儗價乽僩儕僢僋乿偱垻晹姲暞偡傞忋揷師榊嫵庼偑敪偡傞僙儕僼偱偡丅
偔偩傜側偄偲偄偊偽偔偩傜側偄偺偱偡偑丄侾俀寧俀侽擔偐傜巒傑偭偨乽傾僀僨儞仌僥傿僥傿乿偭偰偄偆嶰塝偠傘傫偺塮夋傕惀旕尒偨偄側偲巚偭偰尨嶌乮偲尵偭偰傕枱夋偱偡偑乧乯傪撉傒傑偟偨丅
偲偭偰傕姶摦偟偰丄杔傕乽孨偵偱偒傞偙偲偑丄孨偑傗傜側偒傖偄偗側偄偙偲側傫偩乿偲巚偭偰丄崱弌棃傞偙偲傪慡椡偱傗偭偰偄偒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅乽崱偱偒傞偙偲乿偭偰傎傫偺嵄嵶側偙偲偟偐偱偒側偄傫偩偗偳丄惛堦攖傗偭偰偄偒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅
|
 |
|
|
| 2003擭12寧25擔乮栘乯 |
| 乽傒傫側丄偦偆尵偭偰傞乿偭偰僂僜偩偤両 |
|
丂乽僀儔僗僩斉儘僕僇儖丒僐儈儏僯働乕僔儑儞亅巕偳傕偲儅僗僞乕偡傞俆侽偺峫偊傞媄弍丒榖偡媄弍乿乮嶰怷備傝偐娔廋丒崌摨弌斉乯傪撉傒巒傔偨丅
丂乽儘僕僇儖丒僐儈儏僯働乕僔儑儞乿偲偄偆偺偼榑棟揑側巚峫偵傕偲偯偔僐儈儏僯働乕僔儑儞偺偙偲偱丄墷暷彅崙偱偼丄偙偺儘僕僇儖丒僐儈儏僯働乕僔儑儞偺僗僉儖傪妉摼偝偣傞偨傔偵乽尵岅媄弍嫵堢乿偑揙掙偟偰峴傢傟偰偄傞偺偩偦偆偱偡丅乽尵岅媄弍乿偲偼丄摙榑偺媄弍丄敪昞偺媄弍丄愢柧暥丄昤幨暥丄儗億乕僩丄榑暥側偳條乆側庬椶偺嶌暥偺媄弍側偺偩偦偆偱偡丅偦偟偰偦偆偟偨媄弍嫵堢傪捠偟偰丄榑棟揑巚峫椡傗暘愅椡丄夝庍椡丄僋儕僥傿僇儖丒僔儞僉儞僌乮斸敾揑巚峫乯側偳偑恎偵晅偔偲偺偙偲丅
丂側偐側偐柺敀偄杮偱偡丅乽傒傫側乿偭偰偩傟丠偲偐丄乽偁傟乿偭偰側偵丠偲偐丄乽偪傚偭偲乿偭偰偳偆偄偆堄枴丠乽乧偲偐乿曎丄乽乧偔傜偄乿側偳晛抜壗婥側偔巊偭偰偟傑偆尵梩偺濨枂偝傪塻偔巜揈丅庡岅傪柧傜偐偵偟偰榖偦偆偲偐丄暥枛傪僉僠儞偲榖偦偆側偳丄庤榖捠栿幰偲偟偰乽偨傔偵側傞乿億僀儞僩偑僀儔僗僩晅偒偱徯夘偝傟偰偄傑偡丅偙偺杮偱庤榖捠栿幰偲偟偰偺帺暘偺擔杮岅傪嵞僠僃僢僋偟偨傜柺敀偄偲巚偄傑偡丅
|
 |
|
|
| 2003擭12寧23擔乮壩乯 |
| 帋偟彂偒亅偦偺俀 |
|
愭擔傕彂偒傑偟偨偑丄庤榖捠栿巑堦師帋尡懳嶔偺曌嫮夛傪傗傝偨偄側偲巚偭偰丄妛廗嵽椏傪廤傔偰偄傑偡丅
偙傟偑丄幚偵戝曄側偺偱偡丅杔偑巑帋尡傪庴偗偨暯惉俈擭崰偲偼塤揇偺嵎丅弌斉偝傟偰偄傞彂愋傕憹偊偨偟丄庤榖娭學偺尋媶夛傗倵倕倐側偳傕偨偔偝傫偁偭偰丄壗偐傜庤傪偮偗偨傜椙偄傗傜乧丅
偲偙傠偑丄傗偭傁傝乧偲偄偆偐丄庤榖捠栿巑帋尡偦偺傕偺傪僗僩儗乕僩偵埖偭偨倵倕倐僒僀僩傗彂愋偭偰傎偲傫偳側偄傫偱偡偹丅偙傟偼丄嬃偒偱偡丅
戭寶帋尡偺帪偵偄偔偮偐偺倵倕倐僒僀僩偵偍悽榖偵側傝傑偟偨偑丄偦偆偟偨僒僀僩偼丄乽帋尡懳嶔乿偲偟偰敿抂偱側偄撪梕側偺偱偡丅儊乕儖僒乕價僗傕廩幚偟偰偰丄掕婜揑偵嵟怴偺庴尡忣曬傪憲偭偰偔傟偨傝偟傑偡丅
偳偆偟偰偙傫側戝曄側偙偲傪偛恊愗偵偟偰偔偩偝傞偺偐乧偲偮偔偯偔姶偠傑偟偨偑丄偦傟偑僀儞僞乕僱僢僩偺偡偛偝側傫偱偡偹丅
庤榖捠栿巑帋尡偺暯惉侾俆擭搙偺庴尡幰悢偼俈係俆柤丅妋偐偵儅僀僫乕側帒奿偱偡傛偹丅堦師帋尡撍攋幰偑偆偪俁俋俉柤側傫偩偦偆偱偡丅偪側傒偵暯惉侾俆擭搙偺戭寶帋尡偺庴尡幰悢偼丄侾俇枩俋丆俇俀俆柤偱偟偨丅
庤榖捠栿巑帋尡偼俀俀俈暘偺侾偱偟偐偁傝傑偣傫丅傑傞偱堎側傞帒奿傪斾傋傞偙偲偵壗偺堄枴傕偁傝傑偣傫偑丄傕偆彮偟戝惃偺庴尡幰偑尰傟偰梸偟偄側偲巚偄傑偡丅
暉巸娭學偺帒奿偱尵偊偽丄幮夛暉巸巑惂搙偼徍榓俇俀擭僗僞乕僩偱偡偐傜丄尦擭奐巒偺巑傛傝俀擭憗偄傢偗偱偡偑丄暯惉侾俆擭侾寧偺庴尡幰悢偑丄俀枩俉丆俁俀俋柤偩偦偆偱丄巑偺俁俉攞丅
偳偆偟偰偙傫側偵奿嵎偑峀偑偭偰偟傑偭偨偺偱偟傚偆偐丠
|
|
|
| 2003擭12寧23擔乮壩乯 |
| 倵倕倐擔婰僗僞乕僩 |
|
blog乮Web Log乯亂僽儘僌乛僽儘僢僌亃偲偄偆偺偑棳峴偭偰偄傞偦偆偱偡丅
乽Web傪巊偭偰岞奐偡傞擔婰丄傕偟偔偼偦偺傛偆側宍幃偱捲偭偨乮Web儁乕僕惂嶌幰偺乯強姶側偳傪弎傋偨Web僒僀僩偺偙偲丅斾妑揑峏怴昿搙偑崅偔乮枅擔丄傕偟偔偼悢擔偲偄偆抁偄僒僀僋儖偱峏怴偝傟傞乯丄惂嶌幰帺恎偑擔乆姶偠偨偙偲傗峴摦儘僌丄巇帠傗庯枴丄嫽枴傪帩偭偰偄傞暘栰側偳偵娭偟偰峫偊偨傝丄峴偭偨傝偟偨偝傑偞傑側帠暱傗庡挘側偳傪丄擔婰偺傛偆側宍偱婰弎偟偰岞奐偟偨傕偺丅屄恖偵傛偭偰塣塩偝傟偰偄傞偙偲偑懡偄丅儁儞偲僲乕僩傪巊偭偨堦斒揑側擔婰挔偲偼堘偄丄傕偲傕偲岞奐偟偰丄墈棗偝傟傞偙偲傪栚揑偲偟偰偄傞偺偱丄暥懱傗撪梕側偳偼丄擔婰偲偄偆傛傝偼丄屄恖揑側忣曬敪怣妶摦偲傕偄偊傞丅乿
偙偺儂乕儉儁乕僕傪嶌惉偡傞偺偵巊梡偟偰偄傞乽俬俛俵儂乕儉儁乕僕丒價儖僟乕乿偑僶乕僕儑儞俉偵側偭偰丄乽倵倕倐擔婰乿婡擻偑晅偄偨両偭偰傫偱丄挷巕偵忔偭偰巹傕傗偭偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅
偲傝偁偊偢丄崱擔偼帋偟彂偒偱偡丅
|
|
|
![]()
![]()